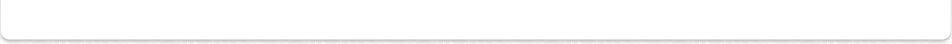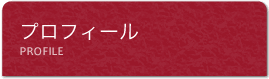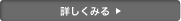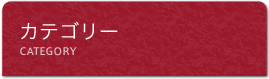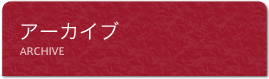- ホーム
- >
- 500人の笑顔を支える、ネット碁席亭日記
根本席亭ブログ 500人の笑顔を支える、ネット碁席亭日記 囲碁の上達方法やイベント情報など、日々の出来事を発信していきます。
2017/12/22
よいお年を
この挨拶をする機会が増えてきた。
次に会うのは新年、という時だけ期間限定で登場する
この言葉の響きは結構好きだ。
発する自分も「よし、いい年を迎えるぞ」と気持ちが前向きになる。
そういえば今年の元旦、実家でのことを思い出した。
4歳になったばかりの姪っ子を隣家に挨拶に連れていった時、
彼女は堂々と挨拶をした。
「よいお年を!」
そのあとに省略されている言葉まで教わらなかったのだろう。
思わぬ視点に周囲の顔がほころんだ。
2017/12/21
時報より正確?
2日連続で87歳のシニア宅を訪れた。
僕はいつも10分ほど前に到着して、1Fのロビーで時間を調整してから
彼が住む23階に向かう。
約束の90秒前に下で部屋番号を押して開錠してもらい
エレベーターであがるとほぼ丁度の時間に玄関前に到着する。
今日は僕が到着すると、既に玄関の扉を開けてニコニコしながら
腕時計を操作する仕草をしていた。
「根本さんの到着にあわせて時計を調整しようと思ってね。
時報より正確だからね」
独特のユーモアだ。信頼されていることが伝わり素直に嬉しい。
ところで僕は、いつも同じ電車に乗って、駅から歩く速度で
微調整して来ていることになっている。
毎回階下で調整しているのはここだけの秘密だ。
2017/12/20
寅さんの役割
今日は87歳の方と対局のあと、奥様と3人で久しぶりの食事を
楽しませて頂いた。
ご夫婦はロシア、ノルウェー、ドイツ、イタリア、イギリスと
1ヶ月に及ぶ強行スケジュールの出張を終えて帰国したばかりだ。
海外での思い出話が一段落したあと、ふと日本の女優の話になった。
「岸恵子って本当にかわいらしくて素敵だったわね」
昔のことを懐かしく思い出しているようだ。
ロシアつながりで栗原小巻の話にもなった。
顔はなんとか浮かぶが僕の世代にはあまり馴染みがない。
しかし僕には強い味方があった。岸恵子も栗原小巻も
昔のトップ女優はみんな寅さんのマドンナなのだ。
ご夫婦は寅さんはあまりご覧になってないようだったが、
僕にも同じ女優に思い入れがあると話の弾みぐあいが違ってくる。
40歳差を超えて女優話を共感できる。
こんな新しい「寅さんの役割」を発見した夜だった。
2017/12/19
旅の前
旅を楽しむスタイルが40代になってかわってきた。
一言でいえば「旅の前」が大きくなった。
旅を始めるまえに旅の楽しみの3割を消化している。
26日から3日間、米原から反時計回りに琵琶湖を車で一周する。
長浜では寅さん第47作のロケ地を巡りたい。
既に何度か見返してポイントは確認した。
中央に浮かぶ竹生島、国宝十一面観音のある向源寺、三井寺や石山寺、
多賀大社など調べ始めると、どんどん興味が広がっていく。
知らないところがあるってこんなに楽しいことなんだと気づく。
まだまだ日本には、そんな場所がたくさん残っている。
2017/12/18
41.1度
恥ずかしながら反省として記しておく。
先週木曜夜、人生で最も高い体温を記録した。
電池が切れかかったテルモ体温計のかわりに
新調したオムロン体温計の最初の検温だった。
彼もいきなり驚いただろう。
僕の電池も切れかかっていた。
火曜夜から5日間、39度を超える高熱が続いた。
抗生剤を2度注射し、抗生物質を投与し続けて昨晩ようやく下がった。
ついこの前、今年は体調を崩していないからまずい、
なんてことをここに書いたのが利いたのだろうか。
とすると今後は筆も慎重にならざるをえない。
丁度2年前、同じ腎盂腎炎で同じお医者さんに
お世話になったので処置が早く助かった。
4日間、ほとんどまともに食べなかったので
新年に向けたデトックスは出来た。
ただこれは今年限りの対策としよう。
そして、これからは、元気で過ごせる1日1日をもっと大事に、
もっと大切に、自分と向き合おう。