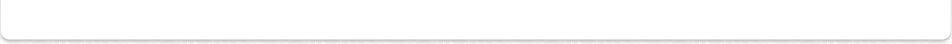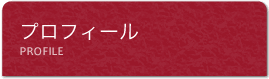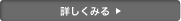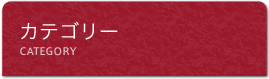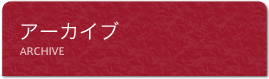- ホーム
- >
- 500人の笑顔を支える、ネット碁席亭日記
根本席亭ブログ 500人の笑顔を支える、ネット碁席亭日記 囲碁の上達方法やイベント情報など、日々の出来事を発信していきます。
2023/10/10
行き当たりばっかし(23)

世界最高のラジウム線出量を誇る山梨の増冨温泉「不老閣」。
両親を連れていった1ヵ月後、今度はつれと再訪した。
坐骨神経痛に悩んでいたので少しでも、ということだ。
例の20℃の岩風呂を経験したつれは、予想通り驚いていた。
―これは修行ね。もしくは罰ゲーム。はいるのに覚悟がいる。
こんな温泉ほかにない。だけどはいっているとだんだん
体が温まってくるから不思議よ。
その通りだ。この小さな岩風呂はある意味日本で3本の指に
はいる名湯だ。~いい湯だな♪~という意味ではない。
決してホッコリはしない。
だがここを目指して全国から何十年と通い続ける人がいる。
ここ「不老閣」の食事は、泊まる人たちの健康を考えてか
揚げ物や豪華なものはなく、身体に優しい野菜中心、
味付け薄目のものが並ぶ。火がついた鍋のふたをとると、
野菜とキノコともずく以外、肉はなかった。
この「もずく鍋」、はじめて食べたが絶品で癖になりそうだ。
2度目の今回は、あるものを別注で頼んでいた。
普段は忘れているが、たまに出会うとテンションあがる。
ショウガやニンニク醤油とあって元気が出そうだ。
馬刺しである。1人前1500円、見事な1皿だ。
―待てよ。こんなのを食べては、元気になっても
温泉の効果かどうかわからないじゃないか。
一瞬頭をよぎったが、ビールをごくりとやったらかき消えた。
*山梨増冨温泉「不老閣」の食事
https://www.furoukaku.jp/oryori.php
2023/10/10
行き当たりばっかし(22)

―あら、浩宮様じゃない。
お袋の声で壁に貼られた何枚かの写真に目をやると
たしかに若かりし浩宮様、いまの天皇陛下が写っていた。
昭和49年と50年、まだ中学生の浩宮様は、2年続けて
この宿、増冨温泉「不老閣」の裏手にある2つの100名山、
瑞牆山と金峰山に登る前に1人で泊まったそうだ。
よくある皇室御用達の豪華な宿ではない。
23部屋のうち部屋にトイレがついているのは数部屋のみ。
あとは合宿所のように、トイレも歯磨きも共同だ。
宿の人に聞いて驚いた。当時泊まった部屋は207号室。
お袋と親父と妹の泊まる部屋だった。弱視の親父のために
トイレ付の部屋を押さえたのが奏功した。
―ここがそうなの。へぇ浩宮様がねぇ。
簡素な部屋の中でお袋がつぶやいた。
こういう偶然は帰宅後のいい土産話になるだろう。
小さい部屋からあぶれた僕は隣の206号室に1人。
ーそうか、ここはSPが泊まったのか。
これはそれほど土産話にはならないだろう。
2023/10/10
行き当たりばっかし(21)
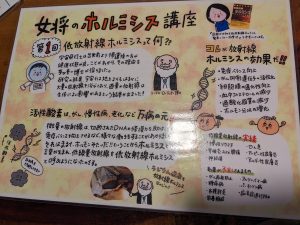
放射線ホルミシス。
聞いたことあるだろうか。
ふとしたきっかけで、昨夏からマイブームとなり
そのあと鳥取の三朝、山梨の増冨、と著名なラジウム泉に
ふれることにもなり、そのブームはいまだ燃え盛っている。
ホルミシスとは、たくさん摂ると身体に毒なものは、
ごく少量だと身体にいい、ということ。
低線量の放射線を浴びると、万病のもととされる活性酸素
をやっつける抗酸化作用が活発になるそうだ。
先日泊まった山梨の増冨温泉「不老閣」の女将は、
温泉のはいり方や健康法など、来客の人の質問に丁寧に答えていた。
本気で宿泊の縁があった方の健康を願っている。
この宿が脅威のリピート率(宿泊者の多くがチェックアウトの時に
次の予約をする)を誇るのもうなずける。
子供のアトピーにも効きますか?と問い合わせの電話には、
では温泉送りますのでまず試してみて、とポリタンクを送ったという。
まだお客さんになっていないお母さん、感激しただろう。
大量だと毒だが、少量だと身体にいい。
そうか…。
何とか笑わせようとくだらないギャグを連発しても
嫌がられるだけだが、力の抜けたちょっとしたことが
思わぬ笑顔を生む。
放射線を見習って、笑いのホルミシス効果をいま、
ひそかに、ねらっている。
山梨増冨温泉「不老閣」女将おすすめ本
https://www.furoukaku.jp/favorite_book.php
2023/10/10
行き当たりばっかし(20)

3月に続き6月も、再度一時帰国した妹と両親、4人で
山梨の増冨温泉に向かった。
前回の山陰旅行では鳥取県の三朝温泉に泊まったが、お袋はここで
「ラジウム温泉」に興味をもち、同じく日本三大ラジウムの
(もう1つは秋田の玉川温泉)増冨に行くことになった。
インパクトは最強だった。宿「不老閣」名物の岩風呂は、宿から
5分ほど山道をあがった先にあった。よくある旅館の岩風呂、
人工的に岩を配置して雰囲気を出すものとは全くちがう。
たまたま岩のくぼみに湧き出して貯まったところに、「あとから」
小屋をたてたものだ。
この岩風呂は朝7時から夕方17時まで。
温泉宿で一番の名物のお風呂が夕方に終了するところを
ほかに知らない。その理由を宿の人に聞いた。
天然岩風呂なので「栓」はなく、毎日夕方にポンプで吸い出して
洗っているのだという。湯量が少ないため、貯まるまでに12時間。
だから夕方で終了なのだ。
大人4人が浸かれるかどうか、という大きさだ。
お風呂の温度は何と20℃。完全な水風呂だ。そばにある41℃の
上がり湯で5分身体をあたためてからでないと厳しい。
あとで宿の人に聞いたら、真冬、マイナス10℃のなか、山を
のぼって元気にこの冷泉にはいる90代の方もいたという。
それも上がり湯がまだなかった頃の話だ。信じられない。
僕のような初心者は、長湯(湯ではないが)厳禁、3分はいって
また身体を暖める、を2,3回程度にしたほうがいいらしい。
事実、僕も宿にもどったあとしばらくは「ぼおっと」した。
ラドンの肯定反応で体がだるくなった。2時間休むとまた
元気になって夕食をおいしく食べたが、すごいパワーだ。
足元から小さな泡がぷくぷくと。意を決して浸かったときは、
冷たくていったいこれは何の罰ゲームだ、という思いだったが、
少したつと不思議と身体が温かくなった。
気泡が身体につくからだろうか。
この温泉のパワーは、西洋医学で完治が難しいとされた多くの人、
多くの症状に対して、奇跡の復活を助けてきた。
全国8千あるという温泉の中で、足元から直接湧き出る
本物の温泉は50か所程度だという。
偶然に感謝である。
増冨温泉「不老閣」
https://www.furoukaku.jp/
2023/10/10
行き当たりばっかし(19)

今までで一番おいしい〇〇に出会う。
最近何かあっただろうか。
50歳をすぎるとさすがに少なくなってきた。
週に何度も食べる食品であれば、さらに難易度はあがる。
昨年秋にオープンした東京は八王子市にある
TOKYO FARM VILLAGE。
実家の徒歩圏ということもあり、何度か既に訪れたが、
ここのヨーグルトが、人生でNO.1となった。
ふたには牛の名前が書いてある。つまり同じ牛からしか
そのヨーグルトは出来ていない。
同じパッケージでも、そして同じ牛でも、季節によって
味が違うヨーグルト、というわけだ。
京王線の山田駅から徒歩数分。新宿から1時間かからない。
目の前でモグモグするジャージー牛にも会える。
ぜひ一度訪れてみてほしい。
TOKYO FARM VILLAGE
https://www.tokyofarmvillage.me/farm
母さん牛の名前いりプレミアムヨーグルト
https://www.isonuma-milk.com/blank-7