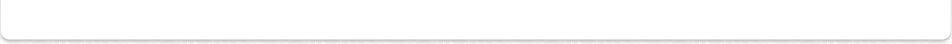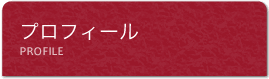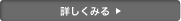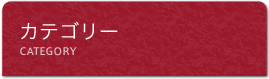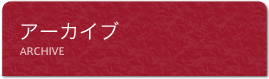- ホーム
- >
- 500人の笑顔を支える、ネット碁席亭日記
根本席亭ブログ 500人の笑顔を支える、ネット碁席亭日記 囲碁の上達方法やイベント情報など、日々の出来事を発信していきます。
2017/09/20
シニアじゃないの?
「昨日ね、大丸のエレベータで『これは障がい者とシニア専用ですよ』
って店員に言われちゃったのよ」
笑顔の2人は80代のご夫婦。
見た目が特に若々しいのは確かだ。
「私達がシニアじゃなければいったい誰がって話よね」
青春とは人生の或る期間を言うのではなく心の様相を言うのだ
サミュエル・ウルマンの詩がうかぶ。
店員はきっと心の若々しさを感じたのだろう。
2017/09/19
お墓の引越し
先週末、はじめてお墓の引越しを経験した。
祖母父、曾祖父母の4人が眠るお墓を祖父が懇意にしていた近くのお寺の
地下納骨堂に移したのだ。
お墓の下には人が立てるほどの深さがあり、そして水が20cmほど
溜まっていたのに驚いた。このお墓はつくって30年以上が経っている。
どうしても湿気が侵入するという。
骨壺に入ってるとはいえ、冷たかっただろう。
祖父の骨壺を開けて確認する。愛用の眼鏡が懐かしかった。
そして久しぶりに会えた気がして嬉しくなった。
元気な祖父母の想い出は自分が学生の頃が中心だ。
いくら高齢化が進んでいるとはいえ、自分が老いを意識しだす中年以降は、
なかなか会える存在ではない。
しかし自分が何歳になっても、想いだして語りかけることはできる。
想い出の井戸があることは幸せだ。
そんな井戸を掘ってエッセイを書いてみたくなった。
2017/09/18
脱敬老
敬老の日に思う。
子供の頃から、お年寄りは敬いなさいと教わって僕らは育った。
しかし「敬う」の本質は教わらなかった。
なぜそう言えるのか。
それは「〇〇を敬いなさい」という教えそのものが「敬う」を
理解していないからだ。敬うとは自発的なもので、強制されるものではない。
敬老を教える際の例で「電車の中で席をゆずる」があった。
だがここで教えるべき精神は「敬う」ではなく「思いやる」だ。
シルバーシートに座っている元気なシニアが、体調の悪そうな若者に
席をゆずってもいいし、シニア同士でゆずりあってもいい。
大事なのは年齢関係なく思いやる心だ。
「敬う」の本質から離れて「敬語」や「お辞儀」といった技術が
広まった結果、それらは感情の伴わない自己防衛の道具となった。
こうして「敬老」が「敬老しない社会」を創ってしまった。
では僕らはこれからどうすればいいのか。
「敬う」から始めないことだ。
「敬う」をゴールの一つにすることだ。
人が人と触れ合い、感情のやりとりが密になるに従って湧いてくる
親しみや友情。その向こうに自然と生まれるのが「敬う」なのだ。
2017/09/17
「老」をポジティブに捉えるのが新しい理由
昔に戻ると新しい。
中村勘三郎の言葉だ。自分の忠臣蔵は、親父の前の台本を使っているのに
新しいと言われるのが面白いと言っていた。
そういえば、オープンカフェって20年ぐらい前から流行ったが、
時代劇を見る限り江戸時代の茶店は皆オープンだった。
哲学者ヘーゲルは「物事の発展は古いものが新たな価値とともに
復活しながら起こる」(らせん階段的)と言っていた。
これから「新しさ」を感じるネタは江戸時代に多くヒントがある。
江戸時代は「老」が大事にされる社会だった。
偉い人は「老中」「大老」と呼ばれた。
そして「老後」とは言わず「老入(おいいれ)」と呼んで、
「老」を終着点ではなく入口と捉えて前向きだった。
現在、「老」が本当に尊ばれているとは言い難いが、
これから「老」をポジティブに捉える、新しい価値観が
どんどん生まれていくだろう。
2017/09/16
懐かしいものがある幸せ
夕方小雨がふるなか、近くの神社で開催の縁日に妻と突撃した。
この近くで小学生3年生から中学2年生まで暮らしていたので、
30年ぶりにまた同じ縁日にきている。
焼き鳥屋台の後ろにテントが張ってあって、座って落ち着ける場所があった。
狭いスペースに丸椅子2つ。雨があたらないように僕らは小さくなりながら
買ってきたばかりのタコ焼きと焼き鳥をつまんだ。
「お母さんにはないしょだよ。こういうところで買って食べるのに
うるさいから」
30数年前、親父が僕にこっそり渡してくれた500円札を想いだす。
あの時の500円は、僕にとって大きなプレゼントだった。
いつも母より厳しい父が、この時は味方になってくれたので、
余計に覚えている。
そんな話を妻としながら、ふとこんな言葉が自然と出た。
「懐かしいものがあるって幸せなことだなぁ」